前回の投稿では、「やさしい」ってどういうことか?
その言葉の意味・定義から、「やさしいがつづかない」理由を紐解きました。
前回までの投稿で、「やさしい」とは
・自分のコントロール権を手放して相手に委ね、かつそれによる結果の責任を引き受けること
・感情論ではなく行動が伴うものであること
であり、痩せてしまいそうなほどにエネルギーが必要なことであることがわかりました。
ですが、それでもやはり「やさしくありたい」という思いは持っていたいものです。
これほどまでにむずかしい「やさしい」を続けることは不可能なのでしょうか?
実は、人はだれしも「やさしい」行動を起こすことができる条件や環境があります。
それも、その条件・環境がそろったとき、人はいとも簡単に「やさしい」を成し遂げてしまうといいます。
今回は、そんな「やさしい」行動を起こすことのできる条件について紹介していきます。
この記事は、哲学研究者であり、東洋大学文学部哲学科教授をされている稲垣諭さんの著書「やさしいがつづかない」を参考にさせていただいています。
今回の記事は第三回の投稿になります。
以前の投稿は、以下の記事で紹介しています。 併せてごらんください。
第一回:【やさしいがつづかない】やさしいがむずかしいのはなぜ?
1.やさしさを発揮できる2つの条件【やさしくなれる条件】
さて、人がいちばんやさしさを発揮できるのはどんな時でしょうか?
その相手は身近な人でしょうか?それとも見ず知らずの他人でしょうか?
人がやさしいを発揮できるとき、そこには2つの意外な条件が存在しているといいます。
人は咄嗟ならやさしくなれる
こんな経験がありますか?
電車の中や道端で、携帯電話やイヤホン、ハンカチなどの手持ちのものを落とした時、それに気づいた人が駆け寄って届けてくれる。
何気ない一コマですが、これは紛れもない「やさしい」行為です。
届けてくれたその人は、その駅では後車する必要がなく、立ち上がらずに席に座っていてもよかったかもしれない。はたまた、道ですれ違い、まったく別方向に向かって歩いていたのかもしれない。
にもかかわらず、自分がコントロールできる時間・行動を、落とし物を届けるという行為のために手放し、委ねてくれたのです。
日本では落とし物の返還率が7割と非常に高いというのはよく耳にする話です。
このような、やらなくても自分には全く問題のなく、何の義務も発生しない行為。
もしかすると落とした相手も、そのままなくしていたとしても「あれ、どこかで落としたかな?まぁいいか。」とあまり気にしない可能性もある。
届ける側からすれば、「もしかしたら落とした人がこの後困るかも?」と想像することができるかもしれませんが、実際にはそんな想像をするよりも前に、真っ先に体が動いて相手に手渡している。
そして、お礼を聞くのも待たずに自分の目的に向かって再び歩みを直し始める。
そんな見返りのない、なにげない「やさしさ」が、実は世の中にはたくさんあふれているのです。
人は咄嗟な出来事では、損得、結果など考えるよりも先にやさしさを発揮できるのかもしれません。
緊急時の共感と連帯感が人をやさしくする
もうひとつ、人が最大限にやさしいを発揮する状況があります。
それは、緊急事態に置かれた時です。
例えば、アパートの自室で急に水が出なくなってしまったとします。
「事前に断水の連絡はなかったのに」と部屋の外に出ると、隣人も同じように断水が気になって外に出てきています。
それまではあいさつを交わすようなことさえなかった隣人でも、緊急時にはお互いに声をかけ、「管理会社に連絡してみます。」と率先して行動してみたり、「それなら自分は水道会社に連絡してみます。」と、自分もできることを探して行動しようとします。
さらには、緊急事態が解決した後も、お互いに気にかけてあいさつを交わすようになる。
こうしたことも、相手を気にかけ、自分の行動を相手に手渡すというやさしさの一つに他なりません。
2.人は非日常で最もやさしくなれる【小さなやさしさ マイクロ・カインドネス】
人がやさしくなれる2つの条件について、
・咄嗟の状況
・緊急時
であることを紹介しました。
ですが、なぜこのような状況下で人はやさしさを発揮できたのでしょうか?
人がやさしくなれる2つの条件から、なぜこんなにも「やさしい」がむずかしいのか?その障害を考えます。
小さくても奇跡的なやさしさ 「マイクロ・カインドネス」
さきほど、落とし物を届ける何気ない一コマを例に、見返りのない咄嗟のやさしさについて紹介しました。
些細なことで困っている人に手を差し伸べるこうした行為を「マイクロ・カインドネス(micro-kindness)」と呼んでいます。文字通りこれは「ちいさなやさしさ」のことです。
出典:株式会社サンマーク出版「やさしいがつづかない」 稲垣諭
人は2分に1回のペースで、誰かにものをとってもらうなどの小さな助けを求めているといいますが、この話ですごいのは、
どうやら要求された人々は、断るよりも7倍も高く、無視するよりも6倍も高い頻度で、手を差し伸べていたのです。
出典:株式会社サンマーク出版「やさしいがつづかない」 稲垣諭
つまり、世の中では圧倒的な頻度で行われる「マイクロ・カインドネス」という小さなやさしさであふれているということになります。
さらに、このやさしさの対象は身近な人に限らなかったといいます。
また、残念ながら断ってしまったという場合でも、そこにははっきりと断る理由があったことがほとんどであったといい、人は特別理由がなければ困ったっている人に手を差し伸べたくなる生き物であるということがわかります。
究極の「マイクロ・カインドネス」
この「マイクロ・カインドネス」が最大限に発揮される事例があります。
それは、災害時です。
災害時、日本人がお互いに協力し合って乗り切ろうとする姿が、海外メディアでも話題になったことがあります。
それは、まさに究極の「マイクロ・カインドネス」と言えます。
災害時には、炊き出しや支援物資の分配など、現地では皆がお互いに協力し合い、今を生きるために団結することができます。
そんなとき、人々の間には壁がなくなり、互いに連帯感や共感が生まれます。
「すべての人が不確かな未来を分かち合い、みんなが同じ境遇にあるせいか、将来を思い悩む人は少なかった。このように心配事から解放されているため、人はその時点で楽に気前よくなれるのだ。なぜなら、私利の追求はたいてい、現在の快適さを守るより、むしろ将来への蓄財を目的としているからだ」
出典:株式会社サンマーク出版「やさしいがつづかない」 稲垣諭
このように、人々は将来の不安から解放されているとき、または気にすることもできないほどに追い詰められているときに、特に「やさしさ」を発揮できるということになります。
3.「やさしい」はそれでもつづかない
ここまで、人がやさしくなれる条件について、日本人としては誇らしく思えるような事例と共に紹介してきました。
しかし、それでも「やさしい」は続かないものだといいます。
それは災害時に発揮される究極のマイクロ・カインドネスでも同じことです。
いったいどういうことでしょうか?
例えば、災害時の炊き出しや支援物資の分配が数週間続いた時のことを考えます。
始めは自ら名乗り出て、力を持ち合って協力し合っていたものの、次第にリーダーのような人や、様々な役割が生まれてきます。
そうなってくると、中にはこうしたやさしさに期待し、当たり前のように扱う人々も出てきます。
こうなると、「そんなつもりでやっていたわけではない」という不満が生まれ、だんだんと関係がギスギスしてくることになります。
「やさしい」とは、コントロール権を手放して相手に委ね、その責任を引き受けること。
まさに、やさしさが利用され、ただ労力を削り取られるだけのものになってしまった瞬間です。
やさしさが日常やルーチンの中では発揮しにくく、非日常や咄嗟の状況で発揮されやすいのはこのためと言えます。
善意が2度、3度と続くと、それを受ける側の人はいずれ善意を当たり前のものと認識し、期待し続けるようになってしまう。
一方、やさしい行為を行った人は、何度も善意を繰り返すことで貸しを作ったと思うようになってしまう。
いつか報われ見返りが来ることを期待するようになり、相手のフリーライドが許せなくなることでやさしが続かなくなってしまう。
双方に共通しているやさしさの壁は、どんなに小さくても見返りを求めないやさしい行動がありがたいものであること、奇跡的にすごいことであることを忘れ、「やさしさ」を利用しようとしてしまうことにありそうです。
4.まとめ
今回は、人がやさしくあることのできる条件から、「やさしい」を妨害する最大の原因にまで迫りました。
・人は見返りを求めない小さなやさしさを発揮する種を持っている。
・やさしいが続かない最大の原因は「やさしさ」を利用しようとしてしまう無意識の欲望である
無意識にやさしさを利用しようとしてしまい、結果として優しさが続かなくなってしまうのであれば、どこまでかんがえてもやさしさを続けることは困難であるように思えてきます。
しかし、お互いのすれ違いによっていずれやさしさが続かなくなる障害が訪れるとしても、最初に起こした見返りを求めない小さなやさしさはたしかに存在していたこと。
真のやさしいを実現するための種は確かに人の心の中にあることは自信を持ってもいいのではないでしょうか。
次回は、それでも「やさしい」を続けるための考え方について紹介していきます。


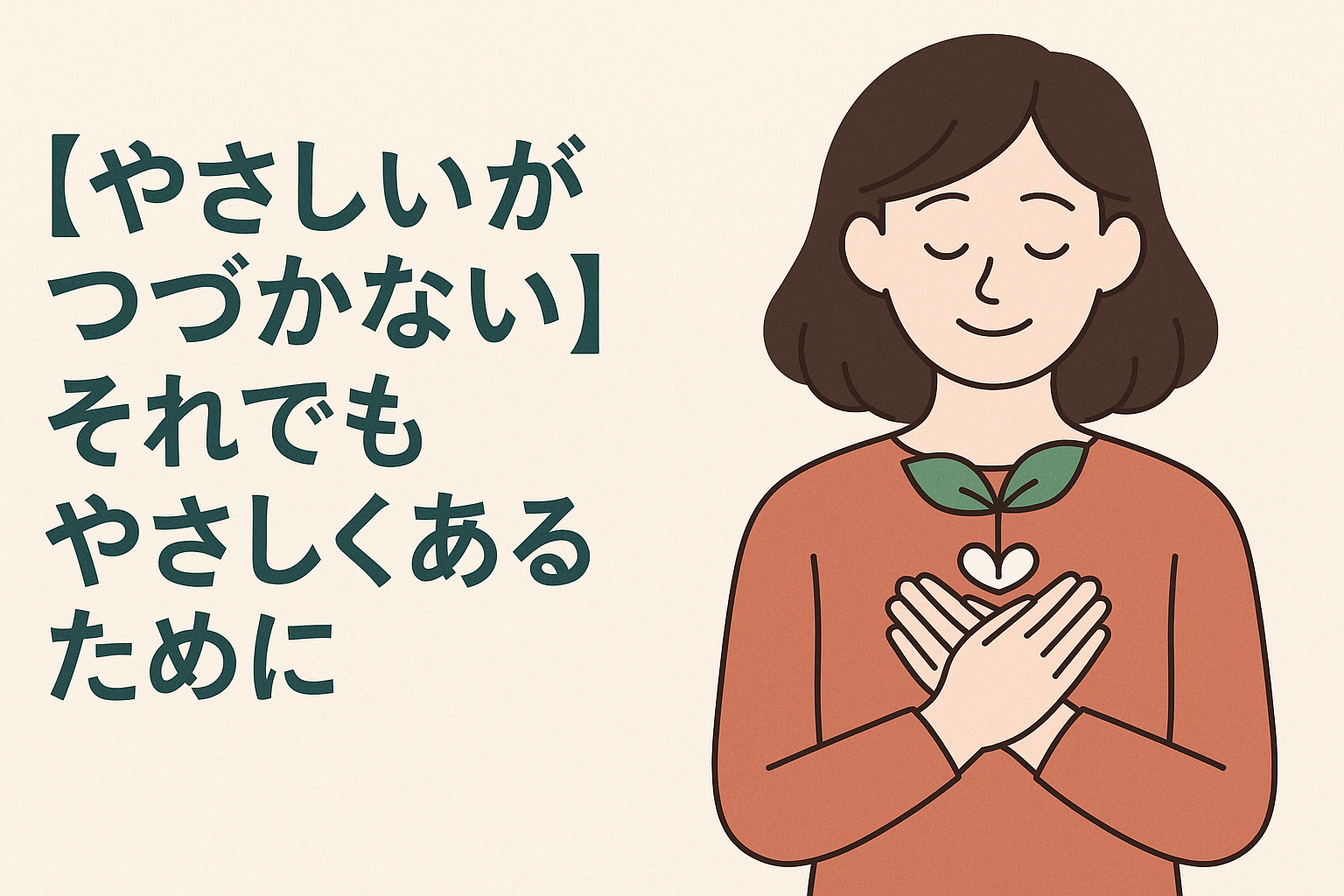
コメント